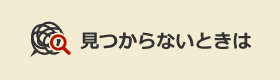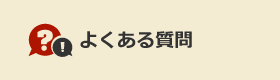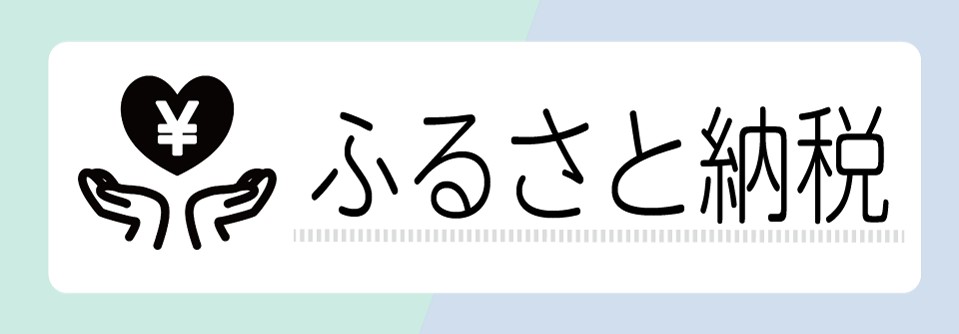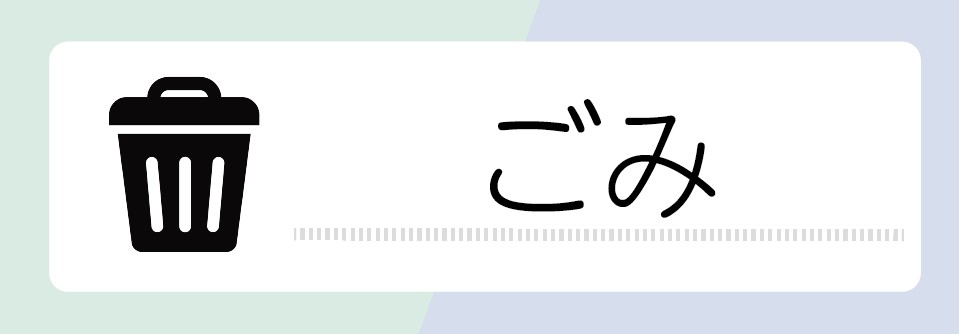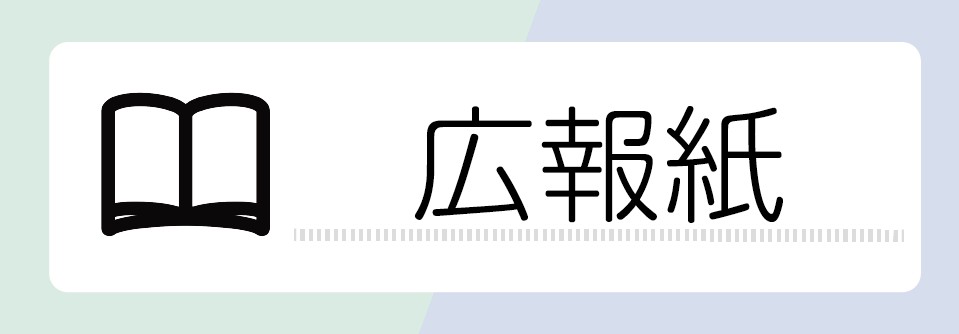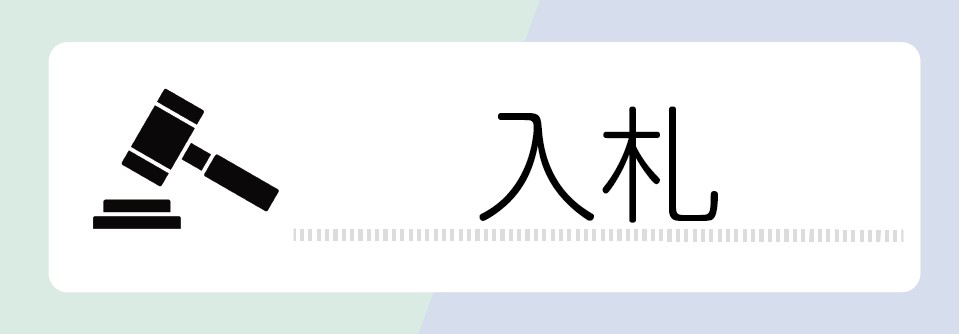火災予防条例改正「林野火災注意報・警報」 (令和8年1月1日~)
印刷用ページを表示する更新日:2026年1月1日更新
火災予防条例改正「林野火災注意報・警報」運用開始 (令和8年1月1日~)
改正の目的
令和7年2月26日に大船渡市で発生した林野火災は、延焼範囲が約3,370ヘクタールとなり、日本の林野火災としては約60年ぶりとなる大規模な林野火災となりました。また、3月には今治市や岡山市でも避難指示が発令されるほどの大規模な林野火災が発生しました。
そこで、人為的な要因での林野火災対策として火災予防条例を改正し、令和8年1月1日より「林野火災注意報・警報」が運用開始となりました。
そこで、人為的な要因での林野火災対策として火災予防条例を改正し、令和8年1月1日より「林野火災注意報・警報」が運用開始となりました。
林野火災注意報・警報
火災が発生しやすい気象条件になった際、火災の発生を未然に防ぐため町長が発令することができるものです。従来の火災警報と制限事項は同じですが、発令される条件が異なり、林野火災の予防上「注意」が必要と判断される気象状況になった際や、予防上「危険」な気象状況になった際に発令します。
【林野火災注意報発令基準】
以下の(1)又は(2)の条件に該当する場合
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ乾燥注意報が発表
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りでない。
【林野火災警報発令基準】
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。
【林野火災注意報発令基準】
以下の(1)又は(2)の条件に該当する場合
(1)前3日間の合計降水量が1mm以下かつ前30日間の合計降水量が30mm以下
(2)前3日間の合計降水量が1mm以下 かつ乾燥注意報が発表
※当日に降水が見込まれる場合や積雪がある場合は、この限りでない。
【林野火災警報発令基準】
林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表された場合。
火の使用の制限
火災予防のため、注意報発令時には以下の制限について努力義務が課せられます。
さらに危険な状況になり警報が発令された際には以下の制限について義務が課せられるため、遵守してください。
1.山林、原野などでは火入れをしない。
2.煙火を消費しない(花火など、火工品を使用しないこと)。
3.屋外では火遊びまたはたき火をしない。
4.屋外では引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしない。
5.山林、原野などの場所で喫煙をしない。
6.残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰または火粉を始末する。
さらに危険な状況になり警報が発令された際には以下の制限について義務が課せられるため、遵守してください。
1.山林、原野などでは火入れをしない。
2.煙火を消費しない(花火など、火工品を使用しないこと)。
3.屋外では火遊びまたはたき火をしない。
4.屋外では引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしない。
5.山林、原野などの場所で喫煙をしない。
6.残火(たばこの吸い殻を含む)、取灰または火粉を始末する。
制限に従わなかった場合の罰則について
林野火災注意報は、警報発令の前段階に位置付けられ、罰則の伴わない努力義務を課すものとなっています。
林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。(※火災警報発令時も同じ)
林野火災警報は、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。(※火災警報発令時も同じ)
発令時の周知方法
林野火災注意報・警報が発令された場合は、音声告知放送などにより周知するとともに、消防車両でのパトロール・広報を行います。