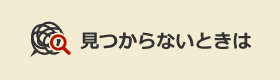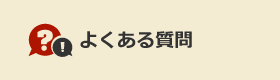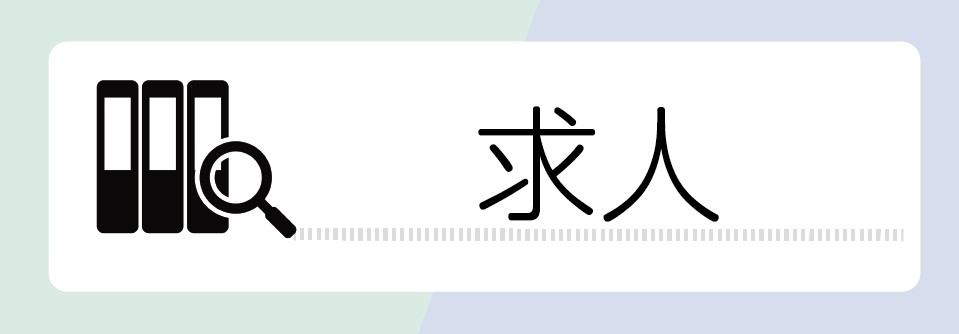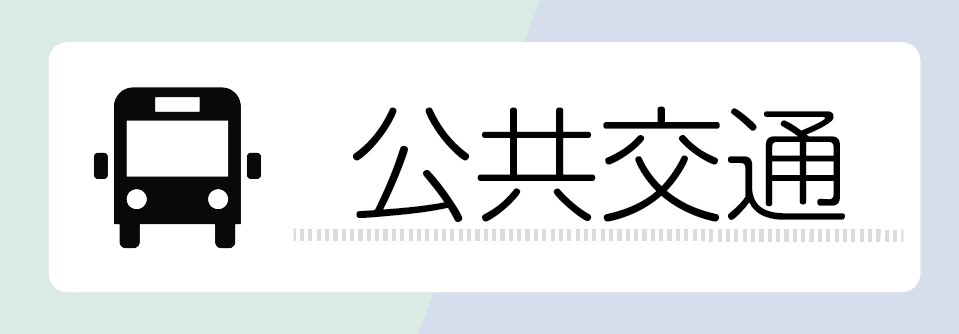児童扶養手当
18歳到達する日以後の最初の3月31日までの児童をもつ父子家庭の父親、母子家庭の母親、または養育者に支給されます。
制度の概要
この制度は、父母の離婚や父親又は母親の死亡等で父親又は母親がいない児童に児童扶養手当を支給し、児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進を図ることが目的です。
手当
所得による支給制限などがありますが、北広島町長の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回、支払月の前月分までの2か月分が振り込まれます。
手当額 (令和7年4月1日から)
全部支給 46,690円
一部支給 46,680円~11,010円(所得に応じて決定されます。)
児童が2人以上の場合は加算があります。
2人目以降 全部支給 11,030円 一部支給 11,020円~5,520円(所得に応じて決定されます。)
※所得制限、公的年金との併給があります。
公的年金との併給
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月から障害基礎年金等を受給している方の手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変わります。
○見直しの内容 令和3年3月分(令和3年5月支払)から
これまで、障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できませんでしたが、令和3年3月分から児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金3級のみを受給している方)は、今までどおり公的年金等の額が、児童扶養手当額よりも低い場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
○手当を受給するための手続
既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。それ以外の方は、申請が必要です。
○支給開始月
通常、手当は申請の翌月から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため、児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
所得制限
請求者本人又は請求者と生計を同じくする扶養義務者等の所得が所得制限限度額以上である場合は、手当の一部又は全部が支給されません。所得制限の対象は、請求者である父親又は母親及び、同居している扶養義務者になります。扶養義務者とは、直系血族及び兄弟姉妹(父母、祖父母、子、兄弟姉妹等)です※1月~9月の認定請求は前々年の所得を対象とします。
所得には、父親又は母親及び児童が受け取った養育費(8割相当額)が含まれます。
また、令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給されている方は、非課税の公的年金給付等を含めた上で所得を算出することになります。
《 所 得 制 限 限 度 額 》
|
扶養親族数 |
請求者本人 |
配 偶 者 扶 養 義 務 者 孤児等の養育者 |
|
|
全部支給 |
一部支給 |
||
|
0人 |
69万円 |
208万円 |
236万円 |
|
1人 |
107万円 |
246万円 |
274万円 |
|
2人 |
145万円 |
284万円 |
312万円 |
|
3人 |
183万円 |
322万円 |
350万円 |
|
以降、1人 増すごとに |
38万円加算 |
38万円加算 |
38万円加算 |
| 加算額 |
〇うち老人扶養親族又は老人控除配偶者がある場合 1人につき10万円加算 〇特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)がある場合 1人につき15万円加算 |
〇扶養親族が2人以上で、うち老人扶養親族がある場合、老人扶養親族1人につき(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は1人を除いた1人につき) 6万円加算 | |
| 主な控除 |
地方税法に規定する次に記載する控除がある場合は、所得金額から控除されます。また、社会保険料相当額として一律8万円が控除されます。 〇障害者 27万円 〇特別障害者 40万円 〇寡婦 27万円(受給権者が母である場合は除く) 〇ひとり親 35万円(受給権者が父又は母である場合は除く) 〇勤労学生 27万円 〇雑損・医療費・小規模企業共済等掛金・配偶者特別控除 当該控除額に相当する額 |
||
※ 所得税法第28条第1項に規定する給与所得又は同法第53条第3項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、給与等の収入金額から給与所得控除額を控除した残額及び公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額の合計額から10万円を控除します。
対象となる児童
対象となる児童は、18歳に到達する日以後の最初の3月31日までです。ただし、児童に政令に定める障がいがある場合は、20歳未満までとなります。
1.父母が婚姻を解消した児童
2.父又は母が死亡した児童
3.父又は母が政令別表第二に定める程度の障がいの状態にある児童
4.父又は母の生死が明らかでない児童
5.父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
6.父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月~)
7.父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
8.母が婚姻によらないで懐胎した児童
9.8に該当するかどうか明らかでない児童
次に該当する場合などは支給されません (※1 ※2)
- 日本国内に住所を有しない場合
- 父又は母が婚姻の届けをしていないが、事実上婚姻関係と同様の状態にある場合
(ひんぱんな定期的な訪問があり、かつ、定期的な生計費の補助を受けている場合には、同居していなくても事実婚が成立しているとして取り扱います。) - 児童が父又は母の配偶者に養育されている場合
(配偶者には、内縁関係にある者も含みます。政令で定める程度の障がいの状態にある者は除きます。) - 児童が父(母)と生計を同じくしている場合
(ただし、父(母)が政令で定める程度の障がいの状態にある場合を除きます。) - 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所及び通園施設等は除く)に入所している場合 など
※1:児童扶養手当を受給している場合、上記に該当すると「資格喪失の届」が必要になります。
※2:「資格喪失の届」を行わずに、手当を受け取られた場合は、その間に支払われた手当は返還していただきます。偽り、その他不正な手段によって手当を受けた場合は、罰せられることがあります。
新規申請に必要な書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
|
認定請求書 所得状況届(7~9月に申請の場合) |
必須 |
| 養育費等に関する申告書 | 必須 |
| 公的年金調書 | 必須 |
| 生計維持方法等確認書 | 必須 |
|
申請者と対象児童の戸籍謄本 |
北広島町で確認できる場合は省略可能 |
| 世帯全員の住民票 | 北広島町で確認できる場合は省略可能 |
| 申請者名義の預金通帳 | 必須 |
| 申請者と対象児童の健康保険証 | 必須 |
|
世帯全員の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カードなど) |
必須 |
|
本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など) |
必須 |
| 年金手帳 | 必要に応じて |
| 公的年金を受給している方は、年金額が確認できる書類 (年金証書、年金額改定通知書など) | 必要に応じて |
| 賃貸契約書の写し(賃貸住宅の場合) | 必要に応じて |
| 光熱水費の契約書又は領収書の写し | 必要に応じて |
| 所得証明書(1月2日以降の転入者は前住所地の所得証明が必要) ※マイナンバーの登録があれば省略できる場合があります。 | 必要に応じて |
| 事実婚解消申立書(未婚の母の場合など) | 必要に応じて |
| 診断書・身体障害者手帳、療育手帳 | 必要に応じて |
| その他 別居監護申立書・世帯分離申立書など | 必要に応じて |
※書類の受付日は、提出すべき書類がすべて揃った日です。
現況届
児童扶養手当の認定を受けている方は、毎年8月に8月1日現在の状況を届け出る必要があります。この届は、児童の養育状況を確認し、前年の所得及び手当を引き続き受給する要件が満たされているかを確認するためのものです。受給者本人が8月31日までに現況届の提出をしてください(手当が全部停止の人も提出が必要です。)。現況届の提出をされないと、11月以降の手当が支給されません。
その他の届出
次のような場合は、こども家庭課へ届け出てください。
1.住所・氏名を変更したとき(北広島町外へ転出するときは、新しい住所地の市区町村担当
課にも届け出てください。)
2.支払金融機関、口座番号、口座名義を変更するとき(変更される預金通帳の写しをご持参
ください。)
3.受給者又は児童が日本国内に住所を有しなくなったとき
4.児童を監護(養育)しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託など)
5.婚姻したとき(婚姻届を提出しなくても、事実上の婚姻関係となった場合も含む)
6.遺棄等で受給の場合は、児童の父又は母が見つかったり、連絡又は仕送り等があったとき
7.児童が父又は母と生計を同じくするようになったとき(父又は母の拘禁が解除された場合
を含む)
8.父又は母の障がいにより受給している場合、その障がいが児童扶養手当法で定められた程
度より軽くなったとき
9.児童又は受給者が死亡したとき
10.監護(養育)する児童の数に増減があったとき
11.障害年金、老齢年金、遺族年金等、公的年金等の申請又は受給ができるようになったとき
(年金額の変更や停止のときを含む)
12.児童が父又は母の受けている公的年金給付等の加算対象となったとき
13.児童が父又は母の死亡による公的年金または遺族補償を受けることができるようになった
とき
14.受給者が扶養義務者(両親・祖父母などの直系血族や兄弟姉妹等)と同居又は別居するよ
うになったとき
15.所得や控除内容等、税金の修正申告をしたとき
16.証書を亡失、棄損したとき など