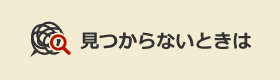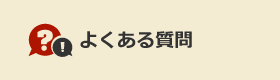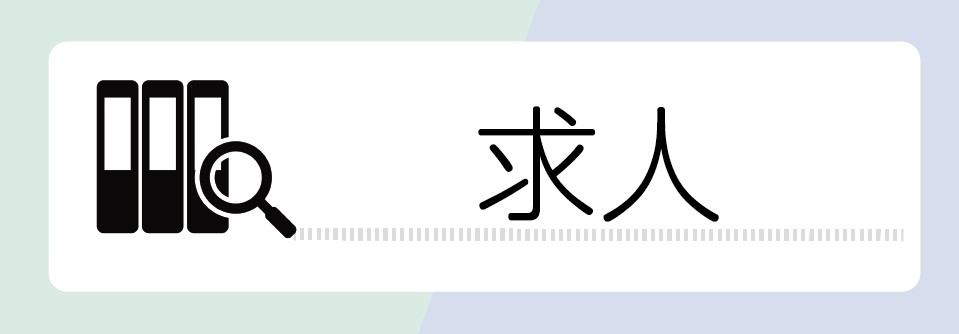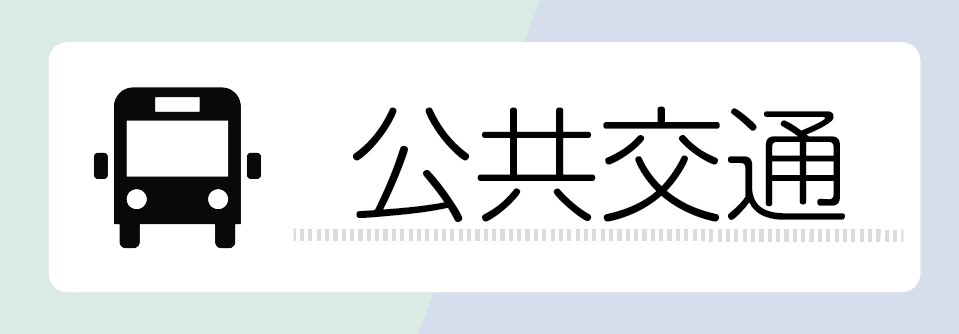町花・町木・町鳥
北広島町の町花
ササユリ
梅雨の湿気に乗って強い香りを放つのがササユリの花です。ラテン語で「日本のユリ」という名前がついていますが、分布は中部地方より西に限られます。
近畿地方よりも北には、花弁に斑点のあるヤマユリが分布しています。ユリの仲間は地下に鱗茎をつくりますが、これがいわゆる「百合根」で、古くから食用にされてきました。百合の仲間はたくさんの種を作りますが、一粒の種の中には芽を出すのに必要なわずかな栄養しかありません。そのため、芽生えたばかりのササユリは、その年に花を咲かせることはできません。それどころか、最初の花を咲かせるのに十分な栄養が貯まるまでには7年から8年かかると言われています。さらに、まわりが籔になり、暗い環境になると、花を咲かせなくなってしまいます。鱗茎に蓄えた栄養を無駄にしないために、小さな葉を1枚だけ付けて、明るくなるのを待つのです。
この写真の株は大きな花を6つも付けていますから、鱗茎はかなり大きくなっているはずです。ササユリは深山ではなく、草刈りがされるような人里に咲く花です。
北広島町内のどこでも見られたと記憶のあるササユリですが、現在では、群生している場所もあれば、「ここにも咲いているね。」と通りすがりに、また、草刈をした後に気付くように、突然現れる(実際はそこに長い間いるのですが)こともあります。 町の花として改めて大切にする気持ちが湧いてくるような気がします。
北広島町の町木
テングシデ
北広島町田原に群生するテングシデは秋には落葉し、幹や枝の屈曲したシルエットを見ることができます。この地域に語り継がれた「炭焼きと天狗の話」などから、くねくねと曲がった幹や枝に「天狗が来てとまる。」と言い伝えられ、「天狗シデ」と呼ばれるようになり、大切に守られてきました。
テングシデはカバノキ科、イヌシデの変種です。イヌシデは関東以西では普通に見られる落葉樹で、幹は真直ぐにのび、町内にも自生しています。テングシデはねじれる、しだれるなどの劣性の遺伝子を持ちながらも、植物に必要な太陽の光や水・土などの条件が整えば、世代交代を可能にし、今日の状態になったものと考えられます。柳や桜など種類によっては「しだれる」木はあるものの、幹まで曲がりくねった木はきわめて珍しく、大変貴重なものです。
通称「天狗シデ」と書きますが、植物名としてはカタカナで「テングシデ」と書き、北広島町田原字灰谷の熊城山東斜面の標高約650m付近に位置し、「大朝のテングシデ群落」として、2000年(平成12年)に国の天然記念物に指定されました。1998年(平成10年)の調査では、指定地内に108本が確認されており、現在は大小あわせると、140~150本以上あると思われます。
1991年(平成3年)の台風により倒木した木をサンプルに推定すると、樹齢はおよそ150年(令和2年現在)で、1870年代前半に発芽したものと思われます。指定地内にある一番大きな木は、石碑の正面にある大木で、周長約3m、樹高およそ16mあります。
北広島町の町鳥


ブッポウソウ
ブッポウソウ(仏法僧)は、本州、四国、九州のほか、沖縄諸島にかけて分布する中型の鳥で、その鮮やかな色彩と独特の鳴き声が特徴です。体長は約30センチメートルで、鮮やかな青緑色の体と橙色のくちばしが目を引きます。日本では夏鳥として知られており、特に繁殖期には、広葉樹林や混交林などの豊かな森林地帯を好んで訪れ、北広島町においても多く見られます。
ブッポウソウは、主に昆虫や小動物を捕食し、森や林に生息します。その特技は、飛んでいる昆虫を空中で捉えることで、その高い飛翔能力が観察されます。巣作りにおいては、天敵から守るために木の穴や岩の隙間などの安全な場所を選び、巣を構築します。
ブッポウソウの鳴き声も非常に特徴的で、「ブッポウ、ブッポウ」と聞こえるため、その名前の由来となっています。この鳴き声は繁殖期に特に頻繁に聞かれ、一度聞くとその独特な音色が記憶に残ります。
北広島町では、ブッポウソウの生息地の保全が進められており、自然保護の観点からも重要な種とされています。また、ブッポウソウの美しい姿や鳴き声は、多くの自然愛好家や鳥類観察者にとって魅力的で、その観察を目的としたエコツーリズムも行われています。
このように、ブッポウソウはその美しい外見とユニークな生態から、多くの人々に愛されている鳥です。その保護活動は、自然環境の保全とともに進められ、今後もその生息地の維持が重要視されています。